友とゆく 韓国ローカル線の旅1. ハモニカ、童謡と木浦の霧鉄道オタクの青春を描くドラマ「特急田中3号」。彼らが列車に乗って旅に出るシーンを目にすると、自分も鉄道の旅に出たくなる。どこか懐かしい風景を探しに国内を回るのも楽しいが、外国の見慣れない列車に揺られながら異文化に触れる旅もまた面白い。今回は、隣国・韓国を縦断する旅に出かけた二人の男たち――山口格郎さんと姜世勲さん――の旅行記を5回に分けてお送りしよう。 文・穴吹史士 撮影・白谷達也 釜山から木浦をめざす黄海へ落ち急ぐ夕陽と競いあって列車は南下、しかし、行き止まりの木浦(モッポ)駅に着いたとき、日はすっかり暮れ、駅前広場の薄暗い隅でイチジクを売る屋台が、いやにわびしく見えた。タクシーを拾い、波止場通りに安い宿を見つけてほしいと運転手に頼む。2人1室で、3万ウォン(約3,800円)が目処である。  韓国縦断の旅に出た山口先生(右)と姜先生 姜世勲(カン・フセン)先生は、1928年生まれの78歳。「6月1日。マリリン・モンローと全く同じ生年月日です」と笑う。この町を訪ねるのは、ほぼ半世紀ぶりである。 初めてやってきたのは、1954年の1月。韓国合同通信のまだ20代の記者だった。韓国で「平和線」と名付けられ、日本では「李承晩ライン」と呼ばれた外国漁船の操業禁止水域を取材するためである。初出動する警備艦にただ1人のジャーナリストとして乗り込み、そのルポと解説は、国内の主要なすべての新聞の新年号紙面に1面トップで掲載された。 4年後には、日本の大洋漁業の漁船を拿捕(だほ)した際、警備隊員が漁船員に包丁で刺されるという事件にも遭遇した。「取材しながら、NHKラジオを聞いていると、臨時ニュースで、大洋漁業の船が正体不明の船に追撃され、SOSを打電している、と繰り返し放送していました」という。戦前の日本支配時代、日本語で教育を受けた姜先生は、日本語を自由に聞き、話す。木浦とその周辺海域は、記者として最も華々しい仕事をした場であると同時に、日本とのついに切れなかった縁を象徴する地でもあった。  光州駅前で木浦行きの汽車を待つ 山口格郎(やまぐち・かくろう)先生も同じ1928年の4月3日生まれ。姜先生と知り合って8年になる。高校、大学で長く英語教師を務め、教え子に民族学校を出た在日韓国・朝鮮人がいたことから、70歳になって韓国語を学び始めた。韓国には10回前後渡航、釜山(プサン)にホームステイしながら、語学学校に通ったこともあり、姜先生を韓国語の師と仰いでいる。 韓国の南西の隅から北東の隅まで、列車やバスをきままに乗り継ぎながら、生きた韓国語に触れてみようと、姜先生と旅に出た。筆者は、山口先生が高校の教師だったころの教え子の1人だ。先生の語学実習を兼ねた韓国旅行にこれまで2度つきあい、今回が3度目である。「姜さんは、ぼくの韓国語をほめてくれたことが、一度もないんです」と山口先生はしきりにこぼす。理由ははっきりしている。ふたりが一緒のときは、言葉の勉強より、居酒屋を飲んで回ることが多かったのだから。 屋台で飲みながら放歌高吟木浦港でも、宿に荷物を放り込んで、さっそく波止場通りの屋台にくりだした。サンナッチ(テナガダコの活き造り)を肴に、いつもの放歌高吟が始まる。山口先生は、こんなときの用意に常にハモニカを携行している。  赤い電飾が妖しげな光を放つ木浦の海鮮屋台 「ね、姜さん、『船頭小唄』やりましょうよ」と山口先生がいい、2人は「お〜れは、河原の枯れすすき〜」と歌い始めた。「姜さんは、『赤城の子守歌』がうまいんだ」。で、「泣くなよしよし、ねんねしな〜」。以下、声を合わせて、「夕焼け小焼け」「七つの子」「紅葉」「琵琶湖周航歌」「七里ケ浜の哀歌」と童謡や唱歌が繰り返される。 「庭の千草も虫の音も……」と山口先生が歌い出すと、姜先生は、「それはもともとアイルランドの民謡なんですね。アイルランドの曲では、ぼくは『ロンドンデリーの歌』が、いちばん好きだな。おおダニー・ボーイ、愛しのわれを……」 歌は際限なく続いたが、歌詞は全部日本語。山口先生の韓国語力向上の道のりは、なお遠そうに見え、海から押し寄せてきた霧に、木浦の夜は深く包まれてゆくのだった。(つづく) 交通:釜山→光州(バス)、光州→木浦(鉄道) 朝食:テンジャンチゲ(具だくさんのみそ汁) 昼食:茹でたジャガイモ 夕食:チョギ(イシモチ)のチゲをメインにした韓定食 宿泊:高麗モーテル(2人1室で1泊3万ウォン=1人約1,900円) 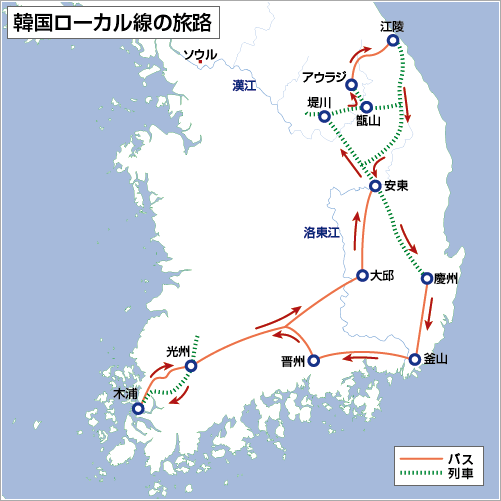  コメントを投稿 コメントを投稿
 トラックバック トラックバック
 テレビウォッチトップへ テレビウォッチトップへ |
横澤彪のチャンネルGメン69
|

