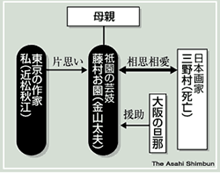|
|
|
|
|
2005/06/04 |
 南山城村をめざし 木津川を渡る=京都府笠置町で それだけ。ほかに何もない。わざわざ出かけるのは酔狂というほかない。 だが、作家の辻原登さん(59)も今春、近くまで訪ねたという。いま朝日新聞に京都を舞台とした小説「花はさくら木」を連載中で、その取材の忙しい合間を縫ってのことだった。 祇園を遊び歩き、当の金山太夫を見知っていた歌人の吉井勇は、このくだりを絶賛し、<秋江君はやっぱり小説家としては第一流>と書き残した。「黒髪」の愛読者なら、ついそこへ行ってみたくなる。 「日本の一流文学者で、秋江の『黒髪』のとりこにならなかった者はいないです。谷崎潤一郎でしょ、大岡昇平でしょ。そして、ぼく……、ははは」と辻原さんはいたずらっぽく話す。自らも、やはり「黒髪」というドキュメンタリー風の小説を書いている。 近松秋江は、決して有名な作家ではない。女性と間違われたり、近松門左衛門と混同されたりするくらいだ。だが、「黒髪」「狂乱」「霜凍る宵」の連作は、「情痴小説の最高峰」「愛欲小説の極致」と評価が定まり、愛着を告白している作家をあげると、水上勉、野坂昭如、久世光彦……。 記者自身も、フランス文学者の奥本大三郎さんと酒を飲んでいて、話題が秋江に及び、手を取りあって泣いたことがあると白状しておく。 情痴、愛欲というものの、露骨な性表現があるわけではない。自分で持てあますほど過剰な情熱、抑制のきかない欲望が相手を暴風雨のように襲う。襲われた相手はたまったものでない。早々に逃げ出す。それをあくまで追跡するところに秋江の本領がある。「私は病的で、離れている女を追究するその事が好きなのですよ」と親しかった徳田秋声に書き送っているほどだ。 先の童仙坊は、「南山城村史」によれば、大正の初めの戸数は47、ふもとへの道は人が荷を背負って歩けるだけの幅しかなかった。「私」は役場で戸籍簿を閲覧、女をかくまっているはずの親類の姓が見あたらないのを確認して、やっと登ってゆくのを断念する。  広津和郎は、こんな秋江を評して、「知恵の果実を食べない前の羞恥心の欠如――恥部を隠さなければならないというような世間並みの思惑が生ずるスキがなかった」といっている。 広津和郎は、こんな秋江を評して、「知恵の果実を食べない前の羞恥心の欠如――恥部を隠さなければならないというような世間並みの思惑が生ずるスキがなかった」といっている。「黒髪」の女・金山太夫は最終的に行方をくらました。行き場を失った過剰な愛は悲惨だ。秋江は悄然と東京に帰ってくる。 「身も心も恋にやつれなどと言いますが、その人はもう、だらりとさがった前髪の下には目ばかりが大きく光り身は骨と皮だけのよう……」。そんな男をマッサージで治療し、後に妻となった故徳田イチさんの回想である。 イチさんとの間に娘2人が生まれると、秋江の愛情は、脇目もふらずそちらに向かった。そう本人が宣言して書いたのが、「子の愛の為に」という作品だ。愛情の対象となった次女の徳田道子さん(80)は、「とくに亡くなった姉を、食べてしまいかねないほど溺愛していました」と証言する。 しかし、過去の女を忘れたわけではなかったらしい。金山太夫母子が落ちぶれ、ネギ1本買えない境遇にあると聞いて、「面倒をみてもいい」と漏らしたという。「改造社から作品集が出たころで、経済的な余裕があったんでしょうが、お人よしもいいところね」と道子さんは笑う。
●eから 新聞社で働き始めてすぐ、仕事で役に立つこともあろうと、新潮社の日本文学全集72巻そろいを古本屋で買った。約2万円、月給のほぼ半分を投じたと記憶する。しかし、出番がないまま、30年余……。 「愛の旅人」を書くに当たって、やっと役に立った。「黒髪」「狂乱」「霜凍る宵」を全部収録しているのだ。購入当時、失恋の傷心の中にあり、この連作を読んで感動したのが、そもそも今回の取材の原点だ。人生、無駄な買い物も無駄な失恋もない。  ●女をを追う未練と執念 ●ふたり ●ぶらり・味わう |
記事の無断転載を禁じます。著作権は朝日新聞社に帰属します。 |
mail to seventh heaven office |