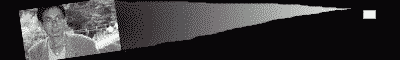|
|
|
|
|
映画 個人的見解 Part2 December 14,1998 |
|
淀川長治氏が亡くなりましたね。思うに、きっと黒澤監督が「俺一人じゃ淋しいから早くコッチへおいでよ」と話し相手に呼んだのに違いありません(なにしろワガママな人だった様ですから)。 淀長氏の追悼番組で、黒澤監督の葬式でインタビューされ、「僕ももうすぐ行くからね、と云ってきました」と語る淀長氏のどこか虚脱した様な表情が思い浮かびます。 皆さんご存知の通り、かなり老衰されていたにも拘わらず、最後迄「日曜映画劇場」の解説を続けただけでなく、これも追悼番組で見たのですが、車イス姿で学生達への講演会で、声を振り絞っている姿は、痛々しくも、いささか鬼気迫るものがありました。 誰かも云っていた通り、彼は単なる「評論家」ナドではなく、「映画の伝道者」というのがふさわしい称号でしょう。 80才を過ぎてなお次作の構想を練っていたという黒澤氏同様、最後迄「夢」と「情熱」を持って生きぬいた「幸せな一生」と云えるのでは……? (ま、途中でリタイアしてのんびりするのも、又善しとも思いますが……)。
前回(9.23)以来、見応えのある作品を3本観ましたので、ご紹介迄。 |
|
|
|
「シンドラーのリスト」に続くスピルバーグの硬派戦争物。「シンドラー〜」の時も「アカデミー狙い」という声があったそうだが、娯楽作だけには飽きたらず、「戦争の真実」を後世や若者に伝えたい、というスピルバーグの「想い」が冒頭30分間も続くノルマンディー上陸作戦の戦闘シーンの目をそむけたくなるリアリズムとしつこさに凝縮されている。(破れた腹からはみ出す内蔵や吹き飛ばされた腕をぶらさげて彷徨う兵士等)「どうだ、本当の戦争ってのは、こんなに残酷なものなんだぜ」と平和ボケした我々に突きつけている感あり。 スピルバーグ監督、トム・ハンクス、マット・デイモン出演というネイムバリューがあるにせよ、このようなHeavyな映画を観るに来る若いカップルは(皮肉でも何でもなく)感心と想う。率直に云って、カップルで見て楽しい映画とも思えない。HAPPYな気分になるというよりは、延々とレクイエムを聴いた後の様な、しみじみした虚しささえ残る映画であった。 「この映画は、英雄の物語ではないし、感傷的な反戦映画でもない。20世紀のすべての戦争で死んでいった者に捧げられた鎮魂歌である」というパンフの評(川本三郎)が一番適切。 さてここで私見を述べると、やはり「1人の兵士を救出する為に8人の兵士が命を懸ける」というストーリイにはややムリがあると思う。当然映画の中でも「何でこんな任務を果たさなければならないのか?」と部下の兵士が問い、トム・ハンクス扮するミラー大尉が「任務を果たして胸を張って帰りたいだけだ」と答えるシーンがある。 1943年、南太平洋海域で、サリバン5人兄弟が同じ艦に乗っていて日本軍に撃沈され、戦死した――という事件から、「兄弟は同じ戦線に送らない」というサリバン法というのが出来た、というのを、この映画の紹介記事を見て初めて知り、驚き感心した。日本では(多分ヨーロッパでも)なかなか出てこない発想であり、やはり「人民の作った国」ならではの発想と思う。 ……が、わざわざ残った1人を救出に行く、というのは、どう考えても不条理であり、リアリティに欠ける――しかし、その「任務の不条理さ」故に「組織とは?」「任務とは?」……といった問いかけが発生し、それによってストーリィの展開に緊張が生まれるという次第。 味方を殺した独兵を捕虜にした後、射殺するか助命するかで仲間割れ寸前となった時、助命を主張したアパム伍長が、ラスト近くで再びその男と出逢い、声をかけられて反射的に射ち殺してしまうシーンは衝撃的でもあり、又どこか物哀しくせつない。 「前歴不詳の任務に忠実な鬼大尉」とされるミラー大尉の前職が実は「高校教師」というのも一寸意外な設定であった。 スピルバーグだからこそ、フィルムカットせず、3時間近い作品となっているが、ハッキリ云ってこれまでのスピルバーグらしくないダラダラした部分もあって、監督の自己満足に付き合わされた感も残る。 |
|
|
|
”Horse Whisperer”(馬にささやく人)という職業(称号?)があるのを、この映画で初めて知った(映画は勉強になる?)。 「”Horse Whisperer”とは馬を手なずける特殊な能力を持った伝説のカウボーイのことで、彼らは馬の心の中を覗き込み、そこに見つけた傷を癒す術を知っていて、病んだ馬の耳に秘密の言葉を囁く、といわれたことからこの名がある」(パンフレットより) そのHorse Whisperer、トム・ブッカー役に、監督も兼ねるロバート・レッドフォード。乗馬の途中、事故に遭い、片脚を無くしただけでなく、生きる気力迄失った娘と、事故のトラウマで人間を寄せつけぬ暴れ馬となった娘の愛馬(ピルグリム号)をトレーラーに乗せて、はるばる3日もかけてモンタナの農場迄トムを尋ね、治療を懇願(強要?)する強引なキャリアウーマンの母親を演じるのが、あの「English Patient」でヒロインを演じたクリスチン・スコット・トーマス。 その夫役に、ピアノレッスンでも妻に裏切られた夫役だったサム・ニール。娘役のスカーレット・ヨハンソンも今後有望株かも――? 田舎の定住者の独身男の所へ、都会(つまり外界)から人妻がやってきて恋が芽生える――というストーリィは、男女逆設定ながら「マディソン郡の橋」を思わせる――という林冬子氏の解説に納得。 物語からして「馬」が準主役級の大きな役割を占めており、この馬の「演技」もなかなか素晴らしいものがあった。特にラスト近く、一旦倒れた馬が、娘のグレースを乗せて再び立ち上がるシーンがなかなか感動的。 もうひとつ、モンタナの大自然もこの映画のおおきな魅力――アメリカの広大さを改めて再認識させられた感あり。(ちなみに、モンタナとはラテン語で「山の多い土地」という意味とか)。 |
|
|
|
久々に「大作」の名にふさわしい作品で、映画の醍醐味を堪能。日、中、仏、米4カ国の総力を結集、とか、制作費60億円とかいう宣伝コピーに、「下手をすると金をかけただけの退屈な歴史ドラマでは?」という危惧も内心感じていたのだが、認識不足というものであった。 冒頭まず出演者の名前を出すタイトルバックからして、小気味良かった。切り傷を思わせるカーブした朱のラインがサクッと画面を切り裂き、それが見る間に出演者の名前の字の一部になってゆく――ここでまず、「おや、なかなかやるじゃないか?」という気にさせられた。 ましてや、始まってみれば、史実の中にフィクションを交えた卓抜なストーリィ展開と幾多の中国人俳優の名演技。壮大な咸陽宮のセットや攻城戦、騎馬車戦の迫力あるスペクタクルシーンに、時を忘れる3時間であった。 始皇帝、呂不韋、公子燕丹、荊軻といった歴史上の人物ばかりでは、結局、いわゆる紙芝居的歴史大河ドラマになってしまいかねない所を、鞏俐(コン・リー)演じる趙姫というフィクションのヒロインを創作し、血の通う人間ドラマに練り上げた陳凱歌と王培公のドラマツルギィーの手腕に脱帽する。(ましてや、陳凱歌は監督と呂不韋役で出演と八面六臂の大活躍)。 考えてみると、この趙姫がいわゆる「狂言回し役」であり、彼女の創作、設定によって、始皇帝、燕丹、荊軻という別々の人間が、ひとつの糸につながり、からみ合ってゆく。趙に人質となっていた秦王政(後の始皇帝)と兄妹の様にして育ち、思いを寄せ合っていた趙姫が、秦が燕を攻める口実作りの為、自ら罪人となって公子燕丹と共に逃亡し、刺客を送り込む算段をする――という正に謀略「埋伏の計」の着想の非凡さ。 かの博識家、荒俣宏の監修ということなので、時代考証は確かなのだろうが、「罪人の頬に焼きゴテで印をつける」という習慣があった様で、趙姫に扮した鞏俐が自ら志願して、その美しい顔に焼き印を入れさせる――というシーンは痛々しくも印象的であった。 又、宦官のローアイが高楼の間に差し渡した板の橋の上を歩かされて、「お許しくだされ……」と恐怖におののいていたのに、イジメ遊びに飽きた始皇帝が姿を消すと、「フン……」と云わんばかりに平然と、又悠々と板橋を渡り切ってゆくシーンには、全く、「部下の言動は全て演技と心得よ」と教えられた気がする。 又、野戦(騎馬車戦)のシーンの迫力も忘れ難い。まるで「ベンハー」での戦車と同じ様なタイプの騎馬車で、やはり中国はローマと地続きの大陸文化なのだと、改めて納得。日本での戦(いくさ)等とはスピードとスペースが違う、という感あり。又、邯鄲城の城攻めシーンでは、城壁に届く程の移動式の大梯子を使って乗り込んでゆく――等、なかなか仕掛けも大仕掛け。 或いは落城した邯鄲城の中に残された子供達を助けてやるつもりで玩具を差し出した始皇帝の顔に、煤まみれの子供(たしか女の子?)が「私達は降参しない!」と叫んで、唾を吐きかけるシーンも印象に残る――ここでカッとしたりせず、「ニタァ〜」と笑う演出がなかなかウマイと思った。(ま、実際にはこんな対面は有り得ないと思うけれど……)。 映画ではこれが伏線となって始皇帝の気持ちが変わり、「わしは復讐が恐い」と、部下に子供達の皆殺し(生き埋め)を指示することになる。ま、「何故、子供達迄殺したのか?」という現代人の問いに対する監督としての解釈と云えよう。 暗殺者である荊軻が、ある事件を機に刺客業から手を引き、いくら頼まれても脅されても「我不殺人」と仏頂面で抵抗する――という設定も、考えてみるとなかなか面白い。「人斬り以蔵」の様に「人を斬りたくてウズウズしている奴」ではドラマにならない。この映画の荊軻は無表情を押し通すかと思うと、時に豹変してやたら剽軽になったりで、「寡黙な壮士」というイメージが混乱する。 始皇帝にしても、これ迄「冷酷、非情、尊大」といった非人間的権力者のイメージしかなかったが、この映画の始皇帝は喜怒哀楽、愛憎共に持った人間として描かれ、甚だ「人間臭い」始皇帝と云える。 天下統一というあれだけの大事業を成し遂げた人物であるからには、決して粗暴等でなく、構想力、指導力、忍耐力を兼ね揃えた大変な器量のある人物であったと思われる――そうした人間があれだけの大殺戮を行って果たしてどう感じていたのか? 或いは時代の違いで、まるきり平気だったのか?
スケールは小粒ながら、はるか後年、日本においても天下統一の為、「阿修羅」と化した(又化さざるを得なかった)信長と考え合わせると、興味深いものがある。あれだけの大殺戮の上に打ち立てられた秦帝国が、始皇帝の死後たった3年、統一以後15年で崩壊してしまったという史実を前にして、深い虚しさを感じるのは、私だけではあるまい。 |
|
Part2 Part1 映画についてのコメントをお待ちしています ohara@dainaga-kk.co.jp |
おはら・よいちろう / 7期天国 / 七福会 mail to seventh heaven office |