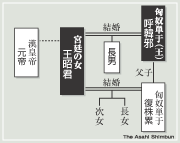|
|
|
|
|
2005/07/23 |
 オルドス市の直道跡。画面手前から奥へ通じていた。 気温零下15度=3月17日、内モンゴル自治区で 地元の歴史作家・鄭天祥(チェン・ティエンシャン)さん(63)が石ころを拾って、ひょいと投げてくれた。表面に模様がある。石ではなく、古い瓦の破片だった。よく見ると畑といわず道といわず瓦が散乱している。秦・漢代、ここに皇帝の離宮があり、直道の基点にもなっていた。 匈奴を攻める軍道として、軍人や捕虜30万人を動員、2年半の工期で紀元前212年に完成した。黄河の大きな湾曲に囲まれたオルドス地方の砂漠と草原を縦断して、現在の包頭市まで約800キロをほぼ真北へ一直線。幅が50メートルもある古代の高速道路だ。「史記」の表現を借りると、「山を崩し、谷を埋める」強引な工事だった。 記録に残る最初の通行者は始皇帝自身だったが、生きて通ったのではなかった。巡視先で亡くなったため、柩で通過した。その後、漢に武帝という武闘派が現れ、本来の用途で存分に利用される。 だが、自然の地形と人間の生活を無視した道路の寿命は短かった。1世紀には史書から消え始め、以降千数百年歴史の中に埋没。浸食されやすい黄土の地形の中で、切れ切れになり、物理的にも消滅しかかっていた。遺構が学術的に注目され始めたのは、ここ20年のことだ。しかし、一般の関心を引かないまま、荒廃が進んでいる。 もし、昭君が通ったのでなければ、直道は殺戮と掠奪に縁取られただけの道で終わっていただろう。また私たちも、地元新聞社が断念したルートを走ってみる気にはならなかった。 直道の跡を探して、明代の長城を越える。考古学的素養のない目に、遺構はあたりの風景と全く区別がつかなかった。2泊3日のドライブで、昭君の苦労をしのぼうというのも、彼女に失礼だったかもしれない。 ただ、現場に着いたとたん日が暮れあっという間に真の闇になったことがあった。古代の夜はこんなふうだったか、光とともに音も失せ、真の静寂というのもあるものだと知った。 「でも、直道の先の方がもっとたいへんだったと思いますよ」と、北京の中国社会科学院で北方・西域の民族史を研究する呉●(ウー・チュオ)教授(62)はいう。当時の単于の本拠は、いまのモンゴル・ウランバートルの西南にあり、さらに1000キロばかり難路を行かなければならなかった。「季節は10月末から11月初めでしょうね」。砂漠では、そのころだけが、日中と夜間の気温が20度と零下20度との範囲に保たれるのだ。 大同市の匈奴史研究家・力高才(リー・カオツァイ)さん(63)によると、昭君の宮女としてのランクは低く、「後宮に残っていたら白髪になるまで飼い殺し。匈奴の王に嫁いだ方が幸せだったかも」と話す。 その幸せは次のようなものだった。 2年後に夫の呼韓邪単于が死亡、部族の習慣に従って、その長男で後継の単于となった復株累(ふくしゅるい)と再婚、12年間連れ添った。先夫との間に、男の子が1人か2人、後の夫との間に2女。 息子の方は、高位に上ったが、若いうちに死亡したらしい。娘2人は、いずれも匈奴の貴族と結婚、しかし、その婿たちが内紛に巻き込まれ、孫たちも殺されたという。 包頭市西郊の直道の終点は、れんが工場になっていた。崩れた烽火台がある丘に上ると、眼下の草原にモンゴル民族の平べったい土まんじゅうの墓が点々、弔旗が風にひるがえっている。南に遠く、黄河が光って見えた。 実は直道に咲いた花は1輪ではなかった。全部で5輪。昭君のほかに、4人の女性が呼韓邪単于に贈られた。 その4人は? 「さー、記録が全く残っていません」とのことである。 ※●は「火」へんに「卓」
●eから 「羊雑」と書いて、「ヤンツァー」と読む。羊肉の断片と内臓のごった煮で、塩でゆで、大皿に盛られて出てくることもあるし、唐辛子のスープとなって現れることもある。「愛の旅人・王昭君」(e1、2面)の舞台・内モンゴルの大衆料理だ。 私の大好物であるが、同行の中国人Wさんは、食べるとおなかをこわしてしまうほど、大嫌い。食事時になると、注文するしないで、毎回激しい攻防を繰り返した。ちなみに、Wさんは漢民族で、私は……、遊牧民族の末裔かな? (穴吹史士) 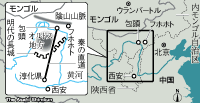 ●花嫁は長城を越えて ●ふたり ●ぶらり・聴く ●映像レポート・中華見聞録 |
記事の無断転載を禁じます。著作権は朝日新聞社に帰属します。 |
mail to seventh heaven office |