ゴルフよもやま話
女人禁制いつまで
ゴルフの語源は何か、また、ゴルフの発祥の地はスコットランドかオランダか、と言うような事がよく議論の対象になります。これには諸説があり、どちらの国もこちらが本家だと譲らず、延々と議論が続いているようですが、先日来読んでいた本の中に、この話題と、かつ ゴルフが発展する過程での裏話などが、面白おかしく且つ興味深く書かれていたので、紹介したいと思います。
まずその発祥については、15世紀半ばにオランダで流行っていた「コルフェン」と言う 氷の上の球遊びが原形のようである。この地へ商売でよく訪れていたスコットランド人が道具を持ち帰り、海に面したリンクスの砂丘・草原の上で行なうようになって現在のゴルフに近い形態となり、そのうち、王侯貴族の間でも大変な人気を得る所となったので、しばしば時の国王によって禁止例が出されるほどになったと言われている。ほかにも諸説紛々とあるようだが、このあたりが 現在では定説となりつつあるようだ。
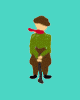
また、スコットランドの砂丘がなぜゴルフコースとして適していたのか、ということには羊と兎が大いに関係していると言う。リンクスにも大きなブッシュになる木が生えていたが、この種子が風に飛ばされて翌春芽を出しても、新芽の段階で兎がきれいに食べてくれる。草原に放牧された羊は自然の草刈り機だったというのである。
最初草っぱらで行われていたゴルフも、徐々にコースが整備され現在の形に近いものとなって行った。と言っても、現在のように機械を使って造られたものではなく、コースそのものは 元々そこにあった地形そのままで、バンカー等も自然の窪みに、吹き寄せられた砂が溜まったものが そのままハザードになったと言われている。
当時のスコットランドではマッチプレーが中心だったので、厳密なルールも特に必要なかったと言われる。お互いに対戦する者同士が了解すればそれで良かったのだ。
当時守るべき掟はただ一つ、「ティーオフしたボールをあるがままに、手で触れることなくホールへ入れる」と言う事だったとか。 また、プレーに際しては、「自分に有利にはふる舞わない」謙虚さを心得としたそうな。
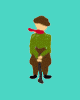
そもそも神が作り給うた自然のリンクスでプレーをするからには、ブッシュの中へ打ち込もうが、ボールがたまたま兎の穴へ入り込もうが、それは自分がした事。自分が打ったボールは自分の責任で打ち続け、あくまでも少ない打数でホールアウトしたものがそのホールの勝ち、と言う事になっていた。
しかし時には そううまく行かない事もある。ある男の打ったボールが、ピクニックに来ていた夫人の敷物の上に停まってしまった。女性の大事な敷物の上のボールをそのまま打つべきかどうか、思案の末 男はボールを拾い上げると「この状態のボールを打つに忍びない。後方に移動させるが、この行為に対し自らに1打の罰を科したい」と申し出た、と言う。この事を聞いたクラブの面々も「その精神や良し」とおおいに賛同したとかで、これが最も古いトラブルの裁定であろうと言われている。
年を経るにつれて、ルールも少しずつ増えて行ったが、それにつれて 各クラブ、各地方バラバラのルールが問題となってきた。それで、ルールを一つに統一しよう、と言う気運が盛り上がり、18世紀後半になって「ロイヤル&エインシェントクラブ」の手で現在のルールの原形となる13ヶ条のルールが作られた、と言われている。
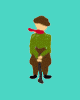
最初の頃は現在では考えられないようなルールがまかり通っていたらしく、ある国では 直径1メートルのカップを許した、とか またある新設コースでは、「フェアウェイに第1打が行かなかった場合には罰無しで打ち直しOK」というローカルルールを定めた事もあると言う。なかでもスコットランド人達を激怒させたのが、今も残る「6インチプレースOK」なるローカルルールであると書かれている。
これは、20世紀に入って急速に経済の発展を見たアメリカにたくさんゴルフ場が作られた結果、当然コース同士の客引き競争が激しくなり「うちのコースでは6インチ置き直してプレーできます。(楽に良いスコアが出せます)」と称して、少しでも客を呼ぼうとする商業主義がもたらした産物であったのであろう。が、これでは、ティーショットを何発でも打ち直しして下さい。と言うコースと何ら変わりない。
実際、アメリカでは、マッチプレーよりもストロークプレーの方が人気があり、いわゆる「スコア至上主義」の傾向がこうした動きを助長したのかもしれない。
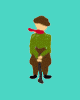
さて、ゴルフを楽しんだのは何も男達だけではない。16世紀のゴルフ事情を記した書物の中にも、既にゴルフに熱中する女たちの話がたくさん紹介されているそうだ。
それでも、記録に名をとどめている最初の女性ゴルファーは、スコットランドのメアリ女王と言う事になっている。フランスの王妃でもあった彼女は、向うから連れて来た小姓に クラブを運ばせていた、この小姓:カデ(cadet)が転じてやがてキャディと呼ばれる様になったのはよくご存知の通り。
ゴルフそのものは男に負けないくらい盛んだったが、クラブライフとなると これは少々話が違うようで、かなり長い間女性蔑視が続いていたようである。
近年に至り女性の権利が認められるに連れて、この傾向は減る方向にあるようだが、厳格な会員制をとっているクラブでは 今でも女人禁制を守っている所が少なくない。(最近外国などでは )女性の方も、それならと女性だけのクラブを作っている所もあり、お互いに居心地の悪い所へ無理に行く必要も無い、と言った所だろうか。
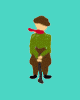
それはさて置き、この問題に当時のスコットランド人がどのくらい頑固だったかを示す良い例として、次のようなエピソードが紹介されている。
―――当時のセントアンドリュースゴルフクラブが女人禁制だったことは言うまでもないが、オールドコースは市有地のため女性でも使用は自由。たまたま婦人選手権試合の当日、天候が急変して 冷たい雨が強風と共に吹き付ける、という最悪の状態。ずぶぬれとなった選手とギャラリーは、寒さに震えながらクラブハウスの壁にへばりつき、雨の通り過ぎるのを待つ他なかった。
と、この時、クラブハウスから支配人が現われて彼女たちに近づいて来た。・・さあ、長年の慣習が破られる時が来たのか? 雨宿りのためだけにでも女性をクラブハウスへ招き入れるのか。・・と、支配人の口を衝いて出た言葉は「ご婦人方、その窓の前には立たないで下さい。外の景色が見えないと、メンバーたちから苦情が出ております」―――
蛇足ながら、前出の「R&Aクラブ」を始め、St.アンドリュースにはいくつものクラブがあるが、これらのクラブがオールドコースを所有している訳ではない。コースはあくまで市の持ち物で 市民のための共有地、と言う事になっていて、市民のプレーフィーは無料だったそうだ。今でも、希望すれば誰でもプレーは出来るが、余りにも希望者が多いので、エントリーは抽選になっていて、当選しないとプレーは出来ない。
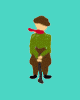
また、大塚和徳氏 作の「ゴルフ五番目の楽しみ」と言う本の中でも、大塚氏が実際にアメリカ留学中に体験したエピソードが紹介されているが、それによると、氏が、ペンシルバニア大への留学を終えて帰国する直前、「パインバレーゴルフクラブ」のプロショップで何かお土産でも買おうと思い立って、家族と一緒に車で訪れたそうな。
「パインバレー」とは、ニュージャージー州クレメントンにあって、世界のコースランキングで常に第1位の座を占め続けている名コース―――ジョージクランプの設計はプロの挑戦をも退け続けている、と言われている。
さて、クラブハウスの前に着き、家族全員が車から降りようとするとグリーンの制服を着た2人のスタッフが「No lady , please!」と叫びながら中から走り出て来て、奥さんは買い物をする事が出来なかった、とか。女性はここの土を踏めない規則になっているので車の中で待つように、と言う訳だ。
現在でも、女性は日曜日の午後以外はプレー禁止だし、食堂は、常時、女人禁制と言う事である。
1999年8月25日記
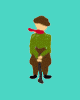
ゴルフクラブの女人禁制、あるいは女性軽視については、まだ続きがある。
当時の社会事情について19世紀末に女権拡張運動で名を馳せたL.コレット女史に「スコットランドでは、女より羊の方が偉く、犬の方が偉いのです。そして、口惜しいことに、苦労して出産した母親より生まれた子供の方が偉いのです」と言う言葉があると言う。それに、ゴルフのクラブと言うのが、もともと居酒屋から生まれたものである以上、当時そのような酒席に女性が列することなど許されたはずも無く、男どもだけが「stag only」の天国で羽を伸ばした、と言う訳だ。
日本でも、さる政務次官が小金井CCの伝統に対して食ってかかった話は以前にも紹介したが、この森山サンは、大相撲の表彰式でも土俵に上がりたがって またまた物議を醸した。この時、当時の双子山理事長がやんわりと、しかも断固として拒否したときの名せりふは後世に残るものだろう。・・「男子のトイレ以外に、1ヶ所くらい女性の入れない場所があってもいいじゃないですか」
蔑視されたのは女性だけではない。アメリカにおける黒人蔑視は、これをも上回り、つい最近まで続いていた。例えば、黒人プロの草分けC.シフォードは、L.Aオープンに優勝しながらついにマスターズに招待されることはなかった。その後の規則改正によって L.エルダーが初めて出場を許されたのは、その後何年も経ってからで、T.ウッズの優勝など、南部の頭の固い連中にとっては考えられないような出来事だったろう。
女子に至っては、問題はもっと深刻で、1960年代、R.ウェストという黒人女子学生が、アマチュアの試合で連戦連勝、プロ転向を宣言したから、より閉鎖性の強かった女子ゴルフ界はさあ大騒ぎ。練習のためにコースへ電話を入れても、「スタートは取れますが、生憎混んでますので 午後4時以降になります」と巧みな口実で締め出しを図った。やむなく、パブリックコースで腕を磨いたそうだが、度重なる嫌がらせと脅迫電話の失望してプロ転向を断念。 黒人女性に対する門戸開放はずっと遅れることになったと言う。
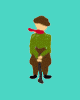
さて、新天地のアメリカに次々とコースが新設され、ゴルフ人口も増えて行った20世紀の初め頃は、ルールやマナーが まだちゃんと行き渡っていなかった時代。数々の迷プレー・珍プレーが記録に残されている。
ある女子のアマチュア競技会に参加したMs.J.ミーハンが126ヤードのショートホールで放ったティーショットは、わずかにショートして手前のクリークに落ちてしまった。1打の罰を払って打ち直せばよいものを、これを知らなかった夫人は、応援に来ていた夫に漕いでもらったボートで川面を流れるボール(当時のボールは水に浮いたと言う。ホントかな)を追いかけ悪戦苦闘。ようやく40打目に対岸へ打ち上げた。ところが、そこに待っていたのは鬱蒼たるブッシュと林。ストロークの勘定を夫に任せた彼女は木の根、兎の巣穴、水溜まり、石の上、茂みの中・・根気よくグリーンをめざした末にホールアウトした時、何と161打と言う不滅の最多記録が達成された、と言う。
時は流れ、プロゴルフの世界でも女性の活躍が始まった1950年代、“Gardenian”誌に連載された「ツアーレポート」は、当時の彼女たちの意気込みを示す貴重な資料となっている。あるショートホールで、グリーン手前の池に11発も連続で放り込んでしまったA.モーリンは、次のショットをしようにも既にすべて使い果たしてしまいボールが無い。頭に来たのかこの彼女、キャディバッグを池に投げ込んですたすたと出口の方へ・・と、不意にUターン。着の身着のままで池に入ってバッグを引き上げた。やれやれ試合放棄だけは思い直したのかと思いきや、バッグの中から車のキーだけ取出して、再びバッグを池に投げ込むと、今度は本当に帰ってしまった、とか。
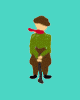
世の東西を問わず、コースで一番嫌われるのがスロープレー。男同士2人でプレーしている前を行く女2人のプレーぶりが、まるでカタツムリのお散歩か というくらいの遅さ。あまりのスローぶりにたまりかねて、ついに男性のうちの一人が抗議に赴いた。が、しばらくすると、首をひねりながら戻って来て曰く「まいったね。前の2人は俺の女房と彼女だったよ」「そいつはまずいな。よし、今度は俺が文句を言ってこよう」
その男もしばらくすると 首をひねりながら戻って来て「不思議なこともあるもんだ。前の2人連れは、俺の女房と彼女だったぜ」
1ヤードでも飛ばしたい、と言う願いもまた 洋の東西を問わぬ永遠の課題であろう。やれ2ピースだ、3ピースだ、メタルミックスだ、とメーカーも売れるボールの開発に明け暮れる今日このごろだが、ゴムを固めた「ガッタパーチャ」が現われるまでは、フェザリー、つまり皮の袋に水鳥の羽根を詰め込んだボールが使われていたのは 良くご存知の通り。ところで、このフェザリーはなかなか良く飛んだらしい。
ボール作りの名手と謳われたアラン・ロバートソンの造ったフェザリーが、あるクラブに保存されていて、絶頂期にあったトミーアーマーが、これを試しに打ってみたところ、約250ヤードのナイスショットになり、「このボールを使って試合に出たいほどだ」と言わせた、とか言われている。実際、361ヤード飛んだ、と言う記録も残っているそうだ。
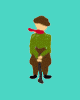
残念なことに、フェザリーには耐久性が無く、また値段が大変高かった。造るのに大変な手間が掛かったのだから無理も無い。今の価格で約1万円位だったと言うから、そうそう簡単に手に入らない。そう、ボール1個がクラブ1本よりも高くついた勘定だ。
だから、この時代のゴルファーは 少しでも安く上げようと、ボールも自分で作る等、涙ぐましい努力を払ったようだ。自分で作るとなると、中へ詰め込む羽根だって吟味の対象になる。一般的にはもっとも手に入りやすかったガチョウの羽根が使われたそうだが、飛距離を求める者はハヤブサの羽根を求め、高い弾道に憧れる者はヒバリ、パットに悩む者はウズラの羽根を求めて東奔西走(ホンマかいな)。貧しくて羽根を買えないあるゴルファーは、娘と女房の髪の毛でボールを作ったと言う話も残っているとか。
・・イヤハヤ。
1999年9月1日記
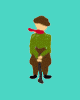
ゴルフで一番大事なショットは何ですか?と聞かれて、誰ですか「ドライバー」と答えた人は? もう殆どが二十数年来のキャリアを誇る七天の諸兄には、そんな人はいないと思うが・・。そう、飛ぶだけだったらバッタでもチョウチョでも飛ぶ。ゴルフは上がってナンボ。パターが入らなければ始まらない(終わらない?)ゲームなのです。で、第3部は、一番大事なパッティングにまつわるエトセトラ・・。
自作のパターにその名を残す、ジョージ・ロウと言う人は、実はプロとしてはそんなにたいした成績も残していないが、「俺が世界一パットのうまい男だ」と自ら吹聴していたくらいだったし、引退してから売り出したパターが、初期の作品は「幻の名器」と騒がれるくらい評判になった。と言って、彼も決して生まれ付いてのパットの名手だった訳ではない。彼は常々、「パッティングだけは練習するほどうまくなる。他のショットと比べても、同じ時間やれば、進歩が確実に現われるのがパッティングだ。」と言い、実際、彼ほどそれを実践した人もいなかったと言われている。
ある朝、B.サイモンと言う評論家が、仲間と一緒のゴルフの折、1番ティへ向う途中の練習グリーンでボールを転がしているロウを見かけ「おはよう」と声をかけた。ハーフが終わって、10番に行く途中でも、彼が同じ場所で練習を続けているのに気付いた。「熱心だね、感心するよ」。
さて、長かった1日のゲームも終わり、ハウスへの帰り道・・。信じられないことに、朝と全く同じ姿勢でロウがパッティングしていた。一同絶句して思わず顔を見合わせたことだったが、やがて誰かが「あれは、ジョージの銅像じゃないか」とつぶやき、恐る恐る近づいてみると、確かにパターが動き、足元から白いボールをホールの方へ転がしている。
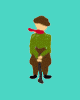
ざっと計算しても、5時間は練習を続けていたことになる。連れの1人が声をかけた。「我々が18ホール廻っているあいだ中ずっとパットの練習を続けていたのか!? よく疲れないものだな」。ロウの答は、「パットで大切なことは、何時間やっても疲れない姿勢だ。30分くらいで疲れるようなら、必ずゲームの後半にパットの調子が悪くなるだろう」
彼は、ゴルフが心理学のゲームだと看破して、技術の鍛練よりも精神鍛練の重要さを「ロウの法則」と呼ばれる10ヶ条に残した。これは今もゴルフ心理学のバイブルのひとつと呼ばれている。
パッティングには集中力が何より要求されるものだが、この事で必ず引き合いに出されるのが、1920年トルーンでの全英女子選手権決勝でのジョイス・ウィザレットだろう。それまで4連勝を続けて無敵と呼ばれたセシル・リーチとガップリ4つに組んだホールマッチは17番を迎え、ジョイスが5メートルのパットのアドレスに入った時、グリーンから30メートルと離れていない線路上を ロンドンからの急行列車が驀進して行った。当然、仕切り直しをするものと思いきや、そのまま彼女はスイングに入り、ゆったりしたストロークから放たれたボールは 吸い込まれるようにカップに消えた。
19歳のジョイスが女王を逆転、初出場でビッグタイトルを獲得した瞬間であったと言う。しかも試合後のインタビューで、17番でのパッティングについて「なぜ仕切り直ししなかったのか」と質問されたジョイスは、「えっ、列車が通ったことなど全然気が付きませんでした」と答えたとか。まさに完璧な集中力と言うより他はない。
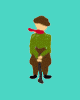
ジョイスの兄ロジャー・ウェザレットもまた、アマチュア界で名手として知られた存在だったが、2人の父ヘンリーの書いた「Perfect Golfer」こそは、ゴルフの神髄を記した名著として絶賛された本である、と言われている。
その彼の2人の子供 ロジャーとジョイスが「ゴルフを始めたい」と言い出した時、H.ウィザレットが始めたレッスンはそれまでの常識を完全に覆したものだった。
最初のうちはショットの練習をさせず、パターだけ。次にランニングアプローチの練習からチップショットの練習、と距離を伸ばして行き、最後にやっと、ドライバーを打たせると言う、世間で行われていたのと全く反対の順でゴルフのショットを教えたそうだ。
パットの練習にしても、まずストロークの練習だけを何百回とやらせた後、やっとボールを使って1メートルのパットの練習。この1メートルの距離が自由自在に打てるようになると、距離を3メートル、7メートルと伸ばし、ついにグリーンの端から端へのロングパット。その距離感を掴んだ所で、7アイアンを渡してランニングアプローチの練習。
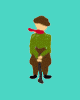
ボールを上げるのは、クラブのロフトがやってくれる、掬い上げるのではない、と言う事が分かって来ると、ウェッジを持たせてチップショットの練習、と言う順番に進めた。
いい加減ドライバーやアイアンの練習をしてみたいと思ったジョイスが父に頼むと、待ってましたと父の答えは「もしお前が、この世で一番上手なゴルファーになって、全部のホールでパー・オン出来たとしても、パットにだけは平均2打掛かるのがゴルフ。総ストロークの半分を占めるグリーン上を制することが肝心。だからまずパットの練習をしなさい」
もう少し、H・ウェザレットは自分の著書の中で補足している。
「ゴルフの本質はデリカシーにある。あの小さなボールを操って直径108ミリのカップへ入れるのにいかに打数を省略するか」
「平均3パットのゴルファーが2パットで収まったら、スコアは一挙に18ストローク縮まるではないか。これを、ショットでカバーしようとすれば、一生かかっても出来ない相談に近い」
「私が子供たちに課した練習は、このデリカシーを最初に植え付けようとした実験だった。小さいショットからだんだん大きなショット、最後にドライバーを習う頃にはスィングの基本が身についているので、容易にマスターできるはず。ショットの練習は、まずピンの近くから始めよ」
9歳で父から手ほどきを受けてゴルフを始めたジョイスは、15歳の頃から、兄と揃って競技会に出場し見事な腕前を披露したと言う。 ウェザレット兄妹のあまりの強さに、取材に訪れた記者の質問に、ジョイスはこう答えた「信じてもらえないかもしれないけど、わたしは1メートルのパットの練習ばかりやったおかげで、それで負けないゴルフを覚えました」。1メートルのパットが百発百中にカップイン出来る人間にとっては、「しびれる」とか「プレッシャー」と言う言葉は縁がないのかもしれない。
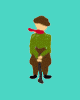
さて、ゴルフは基本的に個人同士で争うゲームだが、各ゴルファーにはもう1人、強−い味方がいる。・・そう、最後はこのキャディにまつわるお話である。
最近 日本のゴルフ場でもキャディの数が足りなくなって、「アメリカン方式」と称して乗用カートでのセルフプレーを取り入れるコースが多くなって来た。 そう、あれはなかなか重労働なのだ。PLのゴルフ場でも、若い女の子にしては結構良い給料を貰っているはずなのだが、次々に辞めていく。聞くと、足を痛めた、腰を悪くした、と肉体労働ならではの悩みが付いて回るものらしい。
アメリカでは、一般のゴルファーはもちろん乗用カートのセルフである。しかし、ツアープロだけは違う。約50人いると言われるツアー専門キャディを雇ってバッグを担がせ、ゲームの中のパートナーとして重宝している。この中でも五本の指に入るトップクラスになると、そこいらのプロが逆立ちしても敵わないほどの造詣と、ルールと心理学に長けている、と言われている。
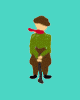
ツアーキャディは、基本の週給プラス選手が獲得した賞金の5パーセントという契約が普通だ。 合計すると、選手の年間獲得賞金の10〜20%近くになり、優勝した時には臨時ボーナスと言うのが普通なので、選手以上に必死なのである。 事実、年収が40万ドルを超える者もいると言う。
あるキャディはシーズンオフになると、かなり高額なフィーを払ってフットボール競技場を借り切り、サイドライン沿いを日がな一日歩き続ける。途中からは目を閉じ、並んで歩く奥さんが誤差の修正をしながら、一歩で1ヤード、正確な歩測ができるよう訓練を積む、とか。 こうして、訓練が終わる頃には、彼の歩幅は せいぜい1センチ位しか狂わないまでになると言う。無論、このデリケートな感覚を損なわないために、新しい靴を買う場合でも慎重に吟味する。正確に1ヤードの歩幅を得るためには、買ったばかりの靴でも 歩測のカンを狂わせるものはすぐ捨ててしまう。
もちろん、靴下に対する気配りも尋常ではなく、暑かろうと寒かろうと、足の裏の感触を狂わさないために、年間を通じて同じ厚さの靴下しか履かない、とも言われている。
また別のキャディは、試合が行われるコースのヤーデージや細かいアンジュレーションなど、びっしり書き込まれたメモを山ほど持っていて、それを銀行の貸し金庫に預けている。ある試合の前夜、不吉な夢で目を覚ました彼は、夜中の2時にもかかわらずガバっと飛び起き服を着ると車でコースへ。懐中電灯を頼りに、くまなくコースの歩測をやり直し、ようやく安心してホテルへ戻った彼の手帳には、去年よりも133ヤードコースが長くなった、と記されたと言う。
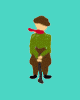
このように、主催者側から渡されたヤーデージのデータを鵜呑みにするような者はまずいない。ある池越えホールのティーに来た時、池を越えて向こう岸のフェアウェイまで、主催者からメモにある数字は、彼の目測よりも短かいように思われた。池があまり深くない、と見てとるや、服を脱ぎ捨てそのまま池の中へ・・。首の近くまで水に浸かりながら、かまわず池を2往復。「歩測してみたら、やっぱり貰ったメモより 10ヤード長かったぜ」
一方、日本のコースに専属のハウスキャディには女性特有の細やかな心遣いがある。ある大手の社長が可愛がって、14年来ずっと指名して付いてもらっているキャディがいたそうだ。ある日ホールアウトすると、このキャディがそっと「差し出がましい事を言うようですが、お体の具合が悪いんじゃありませんか」。驚いた社長が「何だね。やぶから棒に?」と尋ねると、「この1週間、いつもより距離が落ちてしまっています。今日も全部、1つずつ大きなクラブをお渡ししました。どこか悪くないか、精密検査を受けられたらどうですか」 念のため、早速病院で検査を受けたら、肝機能に異常が発見されたというから驚き。
また、ある芸能人は、「最近 目がお悪いんじゃないですか。パットのお上手な方なのに、ラインが全々違ってますよ」と言われて、すぐ眼科の精密検査を受けた所、緑内障になりかかっていたが、処置が早かったので事無きを得たと言うのだ。
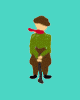
1830年頃には、すでに優秀なプロのキャディが記録に残っている。 W.ガンと呼ばれた男は、グリーンでのパッティングの読みから、客の腕に合わせたクラブの選択、ゲームの組み立てまで引き受けて、「彼が付くと負ける気がしない」と評判になり、キャディーフィーにプレミアが付くほどだったとか。
セント・アンドリュースの名物キャディー:ティップ・アンダーソンが、先日NHKのBSに出てインタビューに答えていたので、ご覧になった方もおられるだろう。 あのA.パーマーと組んだ S.Aでの全英オープンでのエピソードは、なかなか面白かったので最後に紹介したい。
・ ・ 初日。当時パー5だった17番ホールで、第2打の残りの距離を聞かれたので「165ヤード」と答えて6番アイアンを渡すと、パーマーはそれで見事2オン。ところが3パットしてしまいただのパー。2日目も3日目も同じ結果だった4日目。同じ距離なのにパーマーは「5番をくれ」という。「それじゃ大きすぎる。グリーンをオーバーします」と反対したのに、そのまま5番で打ってグリーンオーバーして道路の上。ところが、そこからパターでカップにピッタリ寄せてバーディーを取ったとか。試合の後で、パーマーは「17番の御蔭で優勝を逃がしたな。だって、3日間まちがったクラブを渡しただろう」と笑いながら彼の肩を叩いて労をねぎらったという。
そう、プロのツアーに限らず、ゴルファーとキャディーは一心同体なのだ。
今回のエピソードは幻冬社刊 「王者のゴルフ」夏坂 健:著より大部分借用しました。
1999年9月7日記
|

