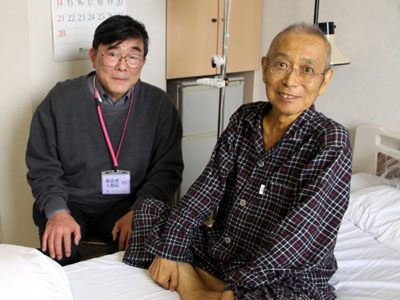プロローグ
「風天 渥美清のうた」
俳優渥美清が俳句をやっている、と聞いたのは、渥美清が亡くなる三年ほど前のことだった。昔の記者クラブ仲間で朝日新聞社の週刊誌「アエラ」の副編集長をしていた穴吹史士と東京・銀座のスナックバーで何年ぶりかで杯を交わした夜だった。
穴吹は後に「週刊朝日」の編集長を務めた。九州・博多で出合った若いころ、能面打ちが、趣味という変わり種のこの男とは、ライバル社ながら後年、新聞から週刊誌の世界へ転じるという同じ道を辿ったこともあって妙にウマがあった。
その夜、何かの拍子で俳句の話になったとき、穴吹はこんな話をした。
「編集部で遊びの句会をやっている。外部の人も加えた素人ばかりの集まりだが、ひょんなことからあの渥美清さんが来るようになった。彼はいつも壁に向かって静かに句を作り、終われば黙って姿を消してしまう」
俳号は風天。言わずと知れたフーテンの寅からきている。当時、渥美清は六十代。「男はつらいよ」シリーズで日本中、誰一人知らぬ者はいない大スターである。
えっ、あの寅さんが俳句!? いったいどんな句を作っているんだろう?
その疑問は、1996年8月4日、渥美清が転移性肺がんで亡くなった直後に出た「アエラ」と「俳句朝日」の誌上で解けた。穴吹ら朝日の句友たちが渥美清への追悼文を書き、「アエラ」句会で作った風天俳句全四十五句を初めて公表したのである。
お遍路が一列に行く虹の中
約三年近く参加した「アエラ句会」最後の日に詠んだこの句は、専門俳人の目にもとまり、講談社の『カラー版新日本大歳時記』に載った。
さらには、漂泊の俳人種田山頭火研究家で俳句評論の第一人者でもある作家村上護の『今日の一句 名句・秀句365日』にも収録され、いつのまにか風天俳句の代表作となった。
「俳句は心の日記」「俳句は人生の履歴書」「俳句は私小説」・・・
わずか十七文字の世界をこんなふうに言う先達もいる。
「俳句ほど作者を離れない文芸はあるまい。一句一句に作者の顔が刻み込まれてある」と言ったのは山頭火だった。
アマチュア俳句といえども、その人が絞り出した作品とその人の人生は分かちがたく結ばれている。
渥美清はどんな親しい友人にも決して私生活を明かさないことで有名な人だった。
ひょっとしたら風天俳句の中にその秘密が隠されているのではないか?私はそんな気がしてきた。
渥美清が逝って今年(2008年)で十二年。下町が生んだ話芸の天才にして国民栄誉賞男の人気は一向に衰えず、この間、数多くの本も出た。しかし、俳句についての記述はほとんどない。
芸名渥美清、役名車寅次郎、本名田所康雄、そして俳号風天。語っても語っても語りつくせない渥美清伝説の中で第四の顔、風天の部分だけがすっぽり抜け落ちている。
「渥美清は『アエラ』以外でも俳句を作っていたようです」
長男健太郎を通して聞いた正子夫人の話である。
私は、厚いベールに包まれた渥美清の心の原風景を覗いてみたくなって、渥美清「最後の贈り物」ともいえる風天俳句探しの旅に出た。

大空出版 1800円
文春文庫にも入れられた
|