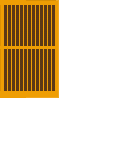吉田の一条通に面して、古い洋館が建っていた。キリスト教の団体が運営する学生寮「地塩寮」で、化け物屋敷のような外観をしていた。その化け物屋敷に足を踏み入れることになったのは、「聖書研究会・ヨブ記講読」というビラを見たからだった。ビラにあったの日時に訪ねると、薄暗い会議室に、柔和な顔をした男が10人ばかり、物静かに着座していた。実は、私にとって、「ヨブ記」などはどうでもよく、中学時代に新約聖書を読んで以来、ずっと抱き続けていた疑問に、誰かが答えてくれるのではないかと思って、そこに行ったのだった。キリストは、磔になったとき、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と叫ぶ。「わが神、わが神、なんぞ我を見捨てたまいし」という意味だという。なんでキリストがそんな泣き言を、というのが、その長年の疑問だった。
一座の世話役のような年配の男は、「その答えは、ヨブ記を最後まで読めばわかります」と、キャッチセールスのような言い方をした。私は、スコラ哲学でも何でも、神学的な解釈がきっとあるはずだから、それを教えてくれさえすれば、この研究会に用はないのだ、ともいってみたが、相手は「いや、ヨブ記を読めば」という線から、一歩も引かなかった。やむなく、その後何回か、講読会に通うことになる。そのころ私は、理学部から文学部のドイツ文学科に転籍したばかりだった。驚いたことに、研究会のメンバーには、ドイツ文学の助教授や大学院生がいて、さらに理学部の教授までいた。そのみんなが、私の境遇をなにかと心配してくれ、その善意が鬱陶しくなって、やがて、講読会から足が遠のいた。
そんなある日、四条通の喫茶店で、灰皿兼用のおみくじ機を引くと、「東北方向から手紙が来る」という卦が現れた。私は、確かにある人物からの手紙を切望しており、来るとすれば南西方向からなのだが……、と、それでも翌日から、郵便受けを気にしていると、手紙が来た。「最近、研究会に姿を見ないので心配しています」──理学部の教授からだった。住所は北白川、方角は三条新町の新聞販売店から見ると東北である。わたしは大いに失望して、返事も出さなかった。いま思うと、たいへん失礼なことをしてしまった。
その後、ヨブ記とも地塩寮とも無縁な人生が続く……、というわけにはゆかなかった。ヨブ記をテーマにした取材で、イスラエルの砂漠の中に出かけたのは1986年だったか。地塩寮と聖書研究会のいきさつまで、その記事に書いてしまった。さらにその10年後、雑誌の編集長をしているとき、ある書家の書いたものが気になって、副編集長に何げなく話したところ、書家と副編集長が、同じ時期、地塩寮に住んでいたことが判明。私を含む3人で、年に2、3回、飲食する仲となっている。問題の地塩寮は、先日、前を通りかかったが、一層凄みをまして健在だった。
余談
入学後1年余り、吉田の一条通りを1本南へ入った中阿達町というところに住んでいた。2階の4畳半1間で月5000円の家賃だった。地塩寮の目と鼻の先、大学へも徒歩5分という好立地だったが、部屋は北向きで、全く日が差さず、冬の寒さは尋常ではなかった。
その下宿屋の3軒ばかり手前の家に、高校で同級だったおかき屋の息子が越してきた。道端でばったり出合って、お互いに驚く。彼は浪人で、京都の予備校へ通っていた。お互いの部屋をひんぱんに行き来するようになり、夜遅くまで話し込んでは、そのまま泊まってゆくということも繰り返した。
彼の部屋は東向きで、北側にも窓があり、とにかく午前中は日が差した。私の部屋の日当たりの悪さをこぼすと、「でも、西日が差すやないか」といわれた。そういわれると、夏、太陽がうんと北に回る季節だけ、強烈な西日が当たり、部屋は蒸し風呂のように茹だった。
夏休みが終わって、実家から下宿へ戻ってくると、鼻が曲がりそうな悪臭が部屋に充満していた。棚に置いていったバターにカビがびっしりつき、それが臭っているのだった。バターが腐ることを初めて知った。しかし、いま思うと、それはチーズみたいに食べられるものだったかもしれない。
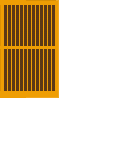
|