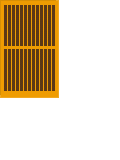その少女の名前を、ときどき思い出そうとするのだが、全く思い出せない。そんなことが、もう30年ばかり続いている。最初の1文字くらいは、出てきそうなものなのに、それさえ思い浮かばない。顔はほぼはっきり思い出せる。それどころか、少女の家の玄関口のたたずまいさえおぼえている。
京都市の南に新しく開かれた住宅街の無計画な道路網で迷いに迷い、その家にたどり着いたとき、日はすでに暮れていた。休日だったが、家には誰もおらず、少女のために描いたパステル画を、戸の透き間にはさんで帰って来た。住所は教えられていたのだろう。しかし、招かれたわけではなく、勝手に押し掛けたのだった。今でいうストーカーである。
その少女とは、三条柳馬場にあるYMCAの社交ダンス教室で出合った。私は同じ新聞屋に住み込んでいたY──中国地方の県立高校からR大に進学したばかりの少年と一緒に、その教室に通い、名前を思い出せない少女Xも友人の女性と2人で、そこに来ていた。Xは大手保険会社の伏見区内の営業所に、その友人は有力銀行の四条河原町の支店に勤めていたが、同じ高校を出てまだ1年、ともに19歳だった。
先方もこちらも2人づつということから、話をするようになり、4人でお茶にゆくようにもなって、当時、手ひどい失恋を経験したばかりだった私は、痛手をごまかすためだったのだろう、Xへの関心を急速に高めていった。家を訪ねてゆくというストーカー的行為も、その果てに起こったことである。だが、Xと私の仲を、後輩のYもXの友人も、温かい目で見てくれていたようだった。
そんなある日、Xの友人を昼食に誘った。彼女が勤める銀行支店は新聞屋からそう遠くなかったので、なにかのついでに声をかけたのだと思う。取り立てて話があったわけではない。が、食堂で向かい合うと、彼女は顔を真っ青にし、がたがた震え始めさえした。最初はなんだかわからなかったが、どうやら、Xについて重大な秘密を知っているらしい。
彼女が口を割ったところによると……、Xがつき合いたいのは私ではなく、後輩のYのほうだという。私の歓心を買うような言動をしたのは、Yに近づくためであり、将を射んと欲すれば馬、のたとえに従ったまでだそうだ。その作戦は成功し、いまXとYは直接2人だけで逢う関係にある。それで、私の思い入れは、Xにとって、もはや不要、それどころか迷惑になっている。私がXの家を訪ねた夜も、2人はデートしていた……。
いま振り返って考えると、Xが私を迷惑に思うのは、道理である。相手の気持ちを確かめず、勝手な片思いにのめり込んでゆくほうが悪い。しかし、そのときは落胆し逆上した。私がその話をYにぶちまけると、どういう心理からかYは私に同情、2人でXを殴りにゆこうということになった。
伏見区内の保険会社営業所に出かけ、Xを呼び出すと、妙にふてくされた表情で、彼女は現れ、私が手を振り上げると、拳で顔を覆い、身を固くして抵抗した。ばれたんだから仕方がない、たたくなり、殴るなり好きにして、といった従容たる態度を予想していた私は、あっけにとられ、しかし、振り上げた手の下ろし場所がなく、頬をなでる程度に、Xをぶった。
それでカタがついた。と思ったのは、私ではなくXだった。その後、堂々とYをデートに誘うようになり、そのうち私のいる時間帯に新聞屋に出入りするようにもなった。私を兄のように慕う時期もあったYは身を縮めていたが、Xはまったく平気。Yの2階の部屋は、私が籠もっている窓のない3畳のちょうど真上に当たり、嬌声が聞こえてくることもあった。
新聞屋のほかの同僚が気の毒がって、私を外に誘い出そうとしてくれたこともあったが、逃げるような形になるのがいやだった。Yのほうはたまりかねて、ついに新聞屋を引き払い、どこかへ引っ越していった。ちゃんと住み込みで働ける場所が見つけられただろうか、と多少気にはなった。以後、Yとは全くの音信不通である。
その後、私を新聞屋に訪ねてきたのは、少女Xのほうだった。1年以上経って、私が新聞社に入ることが決まった直後、誰からその話を聞いたのか、お祝いを言いにきたという。「ああそうですか」と答える以上、とくに言葉も交わさず、三条烏丸の角まで送ってゆくと、「性格、変わらへんね」と言われた。彼女の訪問の真意は、いまもって不明である。
私が少女Xの名前を思い出せないのは、その存在を記憶の中から完全に抹殺したいと無意識に考え続けてきた結果だろう。少女Xと少年Y。いまも一緒にいるのだろうか。いずれにしろ、2人とも50は過ぎているはずである。
余談
京都に仕事で出かけたついでに、東洞院と烏丸、四条と御池に囲まれた昔の配達区域をぶらぶら歩いてみた。京都らしい面影を最も濃く残していたこの界隈から、町家と路地が姿を消し、高層ビルと駐車場ばかりになっていたのが、哀しかった。この稿の2回目に書いた、六角堂の隣の愛染院までなくなっていた。どこかへ引っ越していったのだろうか。
なくなっていたといえば、三条新町のA新聞販売店もなくなったいた。旧店主が廃業したことは、社内の販売担当者から聞いてはいた。しかし、経営者が替わっただけだと思っていた。成績が悪かったり、老齢で経営に情熱を失った店主が更迭されることはときどきある。でも、店そのものがなくなっていたので、とても驚いた。
その店は、私が担当していた区域が典型だったが、京都の銀行や大店が集中する1等地を抱えて、京都でも「御三家」に数えられる名店だった。AERAの創刊時、契約コンクールで全国有数の成績をあげ、表彰されるほど、力があった。当時、AERAにいた私は、同僚が墨で書いている表彰状に店の名を見つけて、そのことを知った。店主に電話すると、「昔ここで配達してたコがつくってる新雑誌やゆうて、店のもんにハッパかけたんや」といっていた。嬉しいことだった。
その店がなくなっていた。建物自体は残っており、かつて私がアトリエに使っていた1階の新聞を仕分けする空間は、そっくり土間の駐車スペースに変わり、軽自動車が頭を突っ込んで止まっていた。看板から判断して、繊維かなにかを扱う商社のようだった。「これで青春も終わったかなとつぶやいて……」。ボロの「大阪で生まれた女」のフレーズを、思わず口ずさんだりしていた。
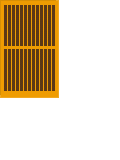
|