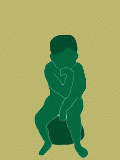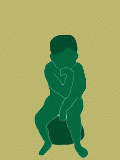ぼやき
2003年2月22日
昔、大阪の漫才に、人生幸郎、生恵幸子というコンビがあった。同世代の大阪の人なら、「そうそう、ぼやき漫才の人生幸郎。おりましたなあ。」とおっしゃることと思う。
インターネットで情報検索をすると、「かすれ声で、世の中の不条理と虐げられている善良な庶民のために演説のような漫才を打って、人気を博した人生幸郎師匠……まあ、みなはん、聞いて下さい……」と出てきた。「……こうやおまへんか?……ほんまにもう、責任者出て来い、ちゅうねん」という語り口に、思わず皆が拍手を送るというようなことであった。幸郎師匠のぼやきには、まるで自分のことのように語りながら、実は世間の声なき声を一生懸命代弁しているところがあり、共感を呼んだのであろう。
世間に対して、あるいは人生に対して、自信を持てそうで持てるに至らない、自分を含めた中年世代の哀愁のようなものを感じたとき、あるいは、ごくささやかな自信めいた割きりが持てたとき、「みなはん、聞いて下さい」と書いてみる、これが私の「吾思う」の流儀である。
ところで、よく言われることであるが、一途に会社人間としてすべてを投げ打って働くのみで、親らしいこと、夫らしいことを見事に何もせず今日に至っているのは、この時代に生きた団塊の世代に身を置いた我々のほぼ共通する心の痛みであり、後ろ髪の引かれるところである。そして、一線を退いた今も、いまさら改めようもない苦々しさが続く。
『親たらず 夫たらずも 生を食み』
『なにゆえに 生をつなぐや なにゆえに』
時折ふっと、そういった自責の念に陥ることがある。いや、そこを通り越して自虐の心境に至って、それはちょっと卑怯であろうと、居心地のいいところに逃げ込んでいる自分を正視する。
『かなわじか 所業放免 諸縁放下』
と言うのも強烈すぎるか。すこし軽く、
『首の皮 一枚でつなぐ 諸縁かな』
と、ひねってみる。
正月の墓参りで、心に響くものあり、
『寒風に 肩を寄せ合う 無縁仏』
『凍る身に 白湯一杓の 極楽や』
と、極楽で締めてみた。
面倒な確定申告もすみ、今晩から二晩続きで同期会である。楽しみにしている。
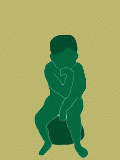
|