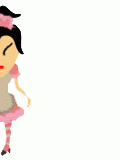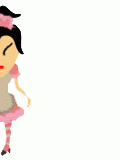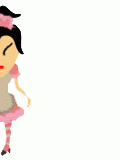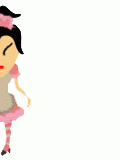地域再生 関西の課題で「なにが必要か、なにを目指すべきか」
1000字のレポート提出
。
ベンチャー経済論レポート
今必要なもの
2006年2月
都市経済政策 M05UB514 佐々木 義之
やってみること。やれることから、やれそうなことからやってみる。
やっているうちに、なにができたか、なにができるのか、つぎになにをしたらええのかみえてくる。
ミクロの地域で考えてみます。
傍観者
先日フェスティバルゲートにおいてシンポジウムがあった。
フェスゲに入居しているアートのNPOが4つある。フェスゲの処理で退去するようになるかもしれない、その時どうするかがテーマでした。3回参加した。
1度目。これまでのいきさつや現状説明がなされた。佐々木先生の基調講演もありました。管轄は交通局でオリックスが管理すると決まったが、諸事情から白紙になったと。
2度目に行ったとき、アート論は彼らのお手の物、当面の問題をさておき盛んな芸術談義やアートとどうやって付き合ってゆくかとの生き方の愚痴に聞こえる論議をやっていた。いらいらして「アートはこの際置いといて、あんたらがここで居る方法を考えたら。そのためにある部分では社会人になることも必要ではありませんか」と、言ってしまった。
3回目、今度も講師の講演があり、フェスゲの使用についてパソコンを使っての総花的な解説がなされた。内容はいいのだがどこまで現実味があるのかそしてあいも変わらず“どうしたらええのかな”の堂堂巡り。
「もうええかげんにしてなんかやったら」と。私自身かまい過ぎたようで、おおいに反省しました。でもなんとなく言いたいことは分って貰えたようです。かれら自身そのことで悩んでいるのですから。
このように書いているわたしは、フェスゲでは傍観者でいられたし評論家であった。
当事者
わたしが当事者である場では勝手な事ばかり言ってはおれません。わが日本橋の商店街や地域のまちづくりにおいても、やはり行動につながる動機や意味付けが要ります。その時フェスゲの連中のように堂堂巡りもします。だれかがやるだろう、なんとかなるやろ、そしてなんにもかわらない旧態が続きます。
それでもいくつかのDOをやっています。来年の春には堺筋をストップさせてストリートフェスタをやります。その準備に街の仲間が奮闘中です。行政は何かをするための手助けをしてくれたら、少なくとも規制・規制で意欲をそがないで欲しい。ほかには、CGアニメ村も作りたい。わたしのやっている工作教室やロボット教室もどう発展させて行くか。当事者としての活動です。
まとめ
いろんなことをやっている街は元気です。いろんな人がいていろんな人が来る街にするにはともかくなにかをすること。やっていれば何が大事かも見えてくる。かつて、“書を捨て町に出でよ”とかいう本があった、さしずめ今ならパソコンをとめて街にでようとでもなる。
ともかく“なんでもやってみよう”が必要なのでは。
|