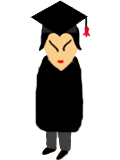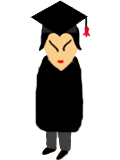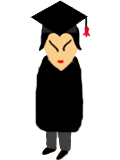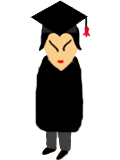修士論文
2008年3月3日
編集長も復帰して、7期天国が更新されて、「何かあるかな」と開きます。
昨年、同級生は2年で出てゆきわたしだけが残った、そして「もうええやろ」と助山もそろそろ卒業する気になって論文を提出した。面接があり、通れば晴れて修士になる。
厳密に言うと論文ではない、リサーチペーパーなるものをかいた。
論文とは、仮説があって論証する。リサーチペーパーはいま通う社会人大学らしく、“現実的な課題を分析し、実施可能な解決策や提案を示すことで、社会にアピールする論文”とある。
原稿用紙100枚ぐらいになるもので、面白くも無い。
7期天国のネタにでもなればと目次と序章だけ。
従来型商店街から創造商店街へ
-日本橋における実践と提言-
2008年1月
大阪市立大学大学院 創造都市研究科
都市政策専攻 都市経済政策研究分野
M05UB514 佐々木義之
【目次】
はじめに
第Ⅰ章 商店街、創造都市-創造商店街にむけて
1.商店街とまちづくり
2.専門店街型商店街の課題
3.大都市における創造都市論-「創造商店街」へ
第Ⅱ章 日本橋の歴史
1.日本橋の変遷
2.最新の変化の分析-サブカルチャーのまちへ
3.ブランドのある街とは
第Ⅲ章 日本橋における組織と人
1.組合と協栄会
2.日本橋まちづくり振興株式会社(まち会社)
第Ⅳ章 日本橋における商店街事業の展開と意義
1.アーケード(=ハード事業)
2.電子工作教室-「学習する創造商店街」
3.日本橋ストリートフェスタ-「参加型の創造商店街」
4.CGアニメ村-「新産業を生む創造商店街」
第Ⅴ章 創造商店街モデルとしての日本橋商店街
1.創造商店街のモデル
2.これから商店街にできること
おわりに-日本橋、いま、そしてこれから
1.ポジティブな方向性
2.手をこまねいていると危機も
3.観光地としての日本橋商店街
4.10年後、いまある日本橋の界隈はどうなっているのか?
はじめに
ヒトそれぞれに個性があるように、商店街にもそれぞれの個性がある。歴史があり、街並みがあり、人もいる・・・それらが総体として街を形成している。ここ数年来、商店街の衰微が盛んにとりざたされ、活性化論議が盛んである。そこでは、同質の結論が導き出されている。さすがに最近では箱物論議は薄れてきた、ところが安易な提案がなされ効果を生み出しているとは思えない。アイデアは秀逸、コンセプトも申し分ない、それでもニーズがないことが多い。多くの案は絵に書いた餅であり、結果としては失敗である。理論と実践の乖離、それが世の中の往々にある現実でもある。
案に独創性があるかどうかはあまり問題ではない。二番煎じ、三番煎じでも結構、集客があるかどうか、商店街が活性化するかどうかが問題なのだ。A商店街で成功しても、Bではパッとしない案がある。逆もある、それぞれのもつ相性・性に合っているかどうかでもある。すべての商店街がもつ個別性により一般名詞でなく固有名詞からの発想が必要である。総論よりも各論。マクロでなくミクロ。理論より実践。机上よりも現場。知識よりも提案。まして、すべてにあてはまるオールマイティの方策はない。
私の実家は、祖父が大正はじめに四天王寺で洋服商を開店し、父が1947年(昭和22年)に日本橋に移転、それから60年になる。わたしは1974年(昭和49年)おやじの急逝で跡を継ぐ。日本橋商店街では、日本橋商店街振興組合の常務理事、でんでんタウン電子工作教室校長、日本橋CGアニメ村村長を務めている。ここでは、日本橋が時代の変遷とともにどのように変わっていくかを分析する。
もしも、わたしが街に愛着がなくなったとき、パッションが消滅した時には,報告も論もわたしからは消えてゆく。いまの日本橋に身を置いているわたしには、そんな時がくることを危惧しないわけではない。様々なマイナスの要素を街は有しても要る。まちづくりから去ってゆく人は、どこにでもある光景でもある。私自身「今後、どう街と向かい合ってゆくか」を考えるためにもペーパーを書き進めていきたい。
「街は劇場である。」と、よくいわれる。台本はあるのか?役者はいる、世間という観客もいる。場は、野外もあれば屋内もある。役者は、商店街にかかわるすべての人が街劇場の役者である。さまざまなひとたちが登場する。劇場は商店街全域である。商店内でも歩道でもどこもかもが舞台になる。演目も多種多様である。
この論文では、大阪・日本橋商店街における筆者の過去の事例を基に、これからの商店街のあり方の一つとして、「従来型の商店街から創造商店街を目指さないといけないのではないか」というモデルを提示することを考える。
以下、第Ⅰ章では、「商店街」とまちづくり、特に専門商店街のこれまでの課題を簡単にみて、創造都市を視野に入れながら、創造的機能をもった「創造商店街」こそ、これからの商店街の発展にもとめられるのではないかという問題提起を行う。
第Ⅱ章では、日本橋の歴史を振り返り、変化の分析もおこなって、古書街→パーツ街→家電街→パソコン街と変遷し、サブカルチャーのまちという顔ができていることを確認する。しかし、単なる「サブカルチャー」「おたく」のまちというだけでなく、若者が注目しているパワーをとらえて、よりクリエイティブな、より高度なブランドのある街へ移行するにはどうするかを考える。
第Ⅲ章では、日本橋における組織と人として、商店街振興組合と協栄会のあり方を説明し、その両者で捉えきることのできない事業の受け皿としてのまち会社(日本橋まちづくり振興株式会社)の位置づけと問題点を検証する。
第Ⅳ章では、筆者がかかわってきた日本橋における商店街事業の展開と意義を振り返る。
ハード事業としてのアーケードによって、商店街の組織化がなされたあと、積極的に展開してきた3つのソフト事業がある。電子工作教室の例からは「学習する創造商店街」とはどのようなものか、日本橋ストリートフェスタの例からは「参加型の創造商店街」とはどのようなものか、CGアニメ村の例からは、「新産業を生む創造商店街」とはどのようなものか、について検討する。
第Ⅴ章では、このような事例を元に、創造商店街モデルを提案する。そして、これから商店街にできることを考えてみたい。
おわりに、日本橋のいまとこれからを考え、ポジティブな方向性と、それだけでなく、手をこまねいていると危機もありうること、観光地としての可能性などを展望する。
以下、全文を読みたい人はクリック
|